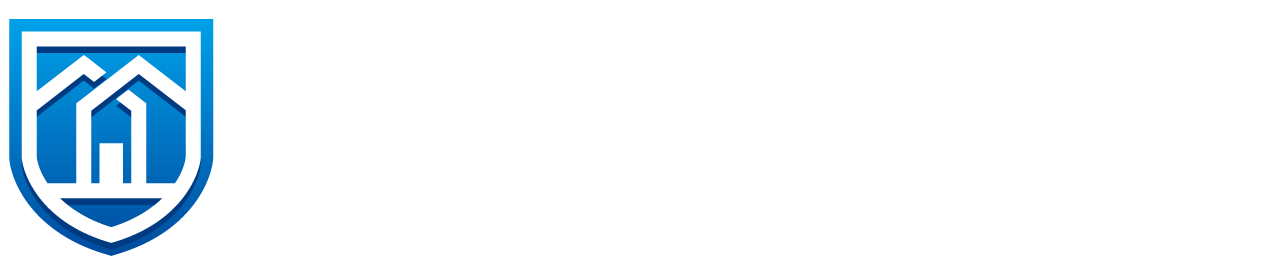1. はじめに
近年、都心部を中心に家賃の値上げが相次いでいます。特にコロナ禍以降の不動産価格の高騰や建築コストの増加により、家賃の値上げを求める大家が増加しているのが現状です。しかし、賃借人(借主)としては、急な家賃の値上げを受け入れたくないケースも多いでしょう。
本記事では、家賃値上げを拒否できるのか、その際の具体的な対処法、そして大家側の視点について詳しく解説します。

2. 家賃の値上げに法的根拠はあるのか?
家賃増額請求の法的根拠
賃貸借契約では、基本的に契約で定められた賃料が適用されますが、民法第611条や借地借家法第32条に基づき、
・大家(賃貸人)は、経済事情の変動や周辺相場の変化を理由に家賃の増額を請求できる
一方で、
・賃借人(借主)はこれに同意する義務はなく、拒否することが可能
という法的枠組みが存在します。
家賃の値上げが認められる条件
家賃の増額請求が法的に認められるためには、以下のような要件を満たす必要があります。
1) 近隣の同種の物件と比べて、現在の家賃が著しく低い
2) 建物や設備の維持管理費が著しく上昇した
3) 土地や建物の価格上昇が家賃の値上げを正当化する
4) 契約書に家賃改定の特約が明記されている
ただし、単に「大家が収益を増やしたい」という理由だけでは認められません。
3. 家賃値上げの拒否方法と賃借人の対応策
① 値上げ要求を拒否する
家賃の値上げを受け入れたくない場合、以下のような対応が可能です。
・「家賃増額請求には応じられません」と明確に伝える
・値上げ要求に合理的な理由がない場合、その旨を指摘する
・現状の賃料が適正であることを示す証拠(周辺の家賃相場データなど)を提示する
このように、値上げの法的根拠が乏しい場合、拒否することは十分可能です。
② 調停・裁判になった場合の対応
大家が賃料増額請求に関する調停や裁判を起こすことも考えられますが、賃借人側には次のような有利な点があります。
・裁判になった場合でも、最終的に裁判所の判断に従えばよい
・調停や裁判は時間と手間がかかるため、大家が途中で諦めるケースも多い
・裁判所は極端な値上げを認めにくい傾向がある
そのため、法律的には賃借人側が強い立場にあると言えます。
③ 多少の値上げに応じるのも一つの選択肢
一方で、交渉の手間や裁判のストレスを考慮し、多少の値上げを受け入れるという選択肢もあります。
例えば、
・「元の家賃+3%程度の値上げなら受け入れる」
・「更新料の免除と引き換えに少しの値上げに応じる」
といった形で妥協することで、無用な対立を避けられるケースもあります。
【↓↓こちらもご参考くださいませ。↓↓】
4. 大家側の視点と交渉術
大家としては、賃貸経営の収益性を確保するために家賃を適正に維持することが重要です。しかし、無理な値上げ要求を行うと、賃借人との関係が悪化し、最悪の場合は退去につながるリスクもあります。
家賃値上げ交渉のポイント
大家側がスムーズに家賃を増額させるためには、
・地域の家賃相場を調査し、正当な理由を説明する
・リフォームや設備の改善を提案し、価値向上をアピールする
・賃借人が納得できる代替案(例えば長期契約の条件変更など)を提示する
といった方法が効果的です。
また、無理に値上げを押し通そうとせず、賃借人との信頼関係を維持することも重要です。

5. まとめ
賃借人の視点
・家賃の値上げは必ずしも受け入れる必要はない
・法的には賃借人の立場が強く、拒否することも可能
・交渉の手間を考え、多少の値上げに応じるのも一つの選択肢
大家の視点
・賃貸市場の動向を踏まえ、適正な家賃設定を行うことが重要
・賃借人が納得できる形で値上げ交渉を進めることが成功の鍵
いずれにせよ、家賃交渉は感情的にならず、冷静かつ合理的に進めることが望ましいです。
家賃値上げについてのトラブルでお困りの方は、ぜひ専門家に相談してみてください。適切な対策を講じることで、最適な解決策を見つけることができます。
【弁護士の一言】
弊所では、賃貸人・賃借人どちらからも、インフレが加速しているコロナ禍以降、この「賃料値上げ問題」の相談数は非常に多いです。
矛盾するようですが、「賃貸人・大家側」には値上げは法的に難しいと回答し、「賃借人・居住者側」には値上げ交渉を拒絶し続けるのはストレスや対応労力もかかるので事実上難しいと回答することが多いです。
結局のところ、法的手続にて完全解決することが難しい紛争類型なのですが、だからこそ、「気合い」といいますか、「事実上の折れない交渉の姿勢」といいますか、「交渉力」が結論に大きな影響を与えている気がします。
【監修:弁護士 山村 暢彦】