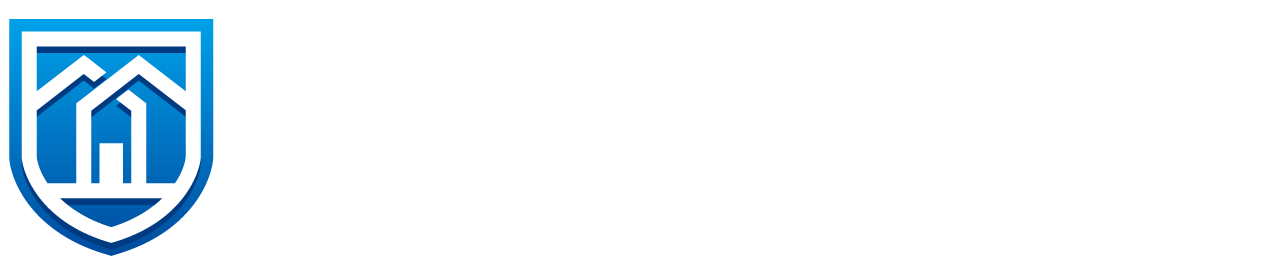相続の問題で弁護士に相談するとき、「この弁護士は本当に自分の味方になってくれるのか?」と不安になることはありませんか?
実は、弁護士には「利益相反(りえきそうはん)」というルールがあり、特定の人の代理をすることで他の相続人に不利益が出る場合、弁護士はその両方の相談を受けることができません。
相続は家族の間での話し合いになることが多いため、弁護士が利益相反になるような立場にならないようにすることが非常に重要です。

相続における「利益相反」って、何?
簡単にいうと、「相続人同士で立場が違うのに、同じ弁護士が両方の味方にはなれない」ということです。
あなたと兄が相続について話し合っているとします。あなたは「親の財産を公平に分けてほしい」と考えている一方で、お兄さんは「自分が家を継ぐから、ほとんどの財産をもらいたい」と主張しているとしましょう。
このとき、同じ弁護士があなたの相談にも乗り、お兄さんの相談にも乗ると、公平な判断ができなくなってしまいます。あなたにとって有利なアドバイスをすると、お兄さんには不利になりますし、その逆も同じです。こうした状況を「利益相反」といいます。
具体的な例で考えてみましょう
① 兄弟で遺産分割でもめている場合
たとえば、あなたが弁護士に「父の遺産をきちんと分けてほしい」と相談し、その後、お兄さんも同じ弁護士に「自分ができるだけ多く遺産をもらいたい」と相談したとします。この場合、弁護士があなたの相談を受けると、お兄さんの相談には乗れません。なぜなら、弁護士は相談者の味方になる必要があり、両方の立場を守ることはできないからです。
② 亡くなった親の借金があるケース
親が亡くなった後、借金があることがわかり、「相続放棄をしたい人」と「相続をする人」 に分かれた場合も、利益相反になります。
たとえば、あなたは「親の借金を引き継ぎたくないから相続放棄したい」と考えていますが、他の相続人は「借金があっても相続する」と考えている場合、同じ弁護士が両方の相談を受けることはできません。相続放棄をする人と、相続をする人では利益が相反してしまうからです。
③ 遺言書があって、内容に納得できない場合
もし、亡くなった親の遺言書があり、「長男に全財産を相続させる」と書かれていたとします。あなたが「この遺言は不公平だから、遺留分(法的に認められた最低限の取り分)を請求したい」と相談すると、その弁護士は長男側の相談には乗れません。なぜなら、あなたの遺留分を認めると長男の取り分が減ることになり、どちらの利益も守ることはできないからです。
弁護士はどうやって利益相反を防ぐの?
相談を受ける前に「利益相反チェック」
弁護士事務所では、相続の相談を受ける前に「相手側(他の相続人)の相談を受けたことがないか」を確認します。もしすでに相手側から相談を受けている場合、その弁護士はあなたの相談を受けることができません。
相談を受けた後に発覚したら、すぐに辞任
万が一、相談を受けた後で「実は相手側の相談も受けていた」と分かった場合、弁護士はすぐに辞任しなければなりません。 「せっかく弁護士に依頼していたのに!」と思うかもしれませんが、弁護士法の要請であり、絶対です。そもそも利益相反に該当しないように、弁護士のほうも注意して受任する必要があります。
相談するときに気をつけるポイント
まずは、弁護士に「他の相続人の相談を受けていませんか?」と確認する
弁護士には正直に答える義務があるので、聞いてみるのが安心です。
兄弟・親族が共通の弁護士を使うことは避ける
兄弟や親族がそれぞれ違う意見を持っている場合は、別々の弁護士に相談するのがベストです。
相手がすでに弁護士をつけている場合は、自分も弁護士を探す
相続トラブルでは、相手側だけが弁護士をつけていると不利になりやすいので、早めに弁護士を探すことが大切です。
利益相反がある場合、別の弁護士を紹介してもらう
弁護士が相談を受けられない場合、他の信頼できる弁護士を紹介してくれることもあります。
まとめ
相続の相談では、弁護士が相続人全員の味方になることはできません。誰か一人の相談に乗ると、他の相続人には不利になる可能性があるため、「利益相反」のルールがしっかり決められています。
相続トラブルをスムーズに解決するためにも、弁護士に相談するときは「利益相反がないか?」を意識し、自分にとってベストなサポートを受けられるようにしましょう。

【弁護士の一言】
「弁護士は利益相反性のある介入ができない」ということが意外と知られていないので、非常に基本的な事例で利益相反についてご紹介しました。相続分野では、度々、「家族の仲裁をしてほしい」という依頼もありますが、そのような依頼の受け方は基本的に「利益相反」に違反して受任できない依頼方法となります。
利益相反については、その際の家庭の状況によっても判断が分かれるケースがありますので、最初はメインで動いている方がご相談にいって、「こういうご依頼の方法は大丈夫ですか?」とか、「●●と●●の立場を一緒に依頼できますか?」など質問されるのが良いと思います。
【監修:弁護士 山村 暢彦】