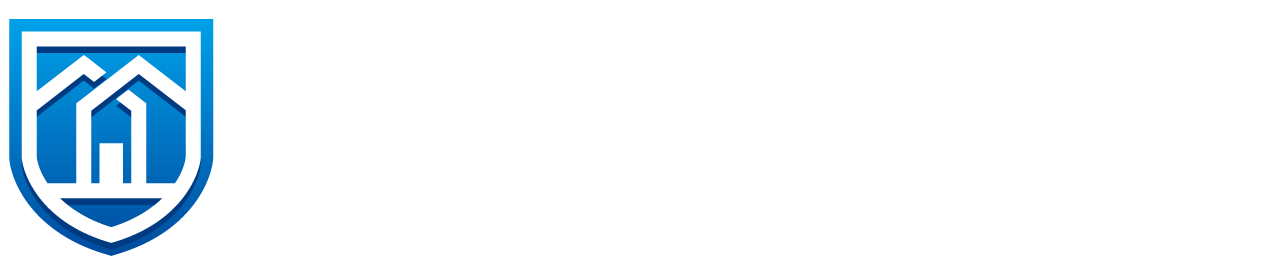「たった数日の支払遅れで契約解除?!」——そんな場面で実際に起きた、土地取引トラブルの事例をご紹介します。
1.契約成立目前、突然のトラブル発生
今回ご相談いただいたのは、海外を拠点にビジネスを展開する海外法人を運営する経営者の方でした。
場所は千葉県内の郊外にある広めの土地。ご高齢の売主様が、引退後の生活資金を確保するために所有地を売却するという背景でした。
条件交渉も終わり、価格も合意済み。水道・電気の整備も完了し、「あとは決済と引渡しだけ」という、契約完了の直前段階でのご相談でした。
ところが、決済日前になって、買主側が「海外送金の都合で、支払いが若干遅れる」と連絡したことをきっかけに、状況は一変します。
2.「期日通りの支払がないなら契約解除」——売主側の強硬姿勢
契約書には「●月●日までに売買代金を支払うこと」と明記されており、売主側(実質的には不動産会社の会長)がその期日を厳格に主張。
買主側はすでに送金手続きも済ませ、遅延といっても数日の話だったのですが、売主側は、
「契約書に違反している以上、解除も当然。手付金は没収する。」と一歩も譲りませんでした。
3.契約書は「最終判断」ではない——交渉による再スタートの模索
買主様としては、「もう少し柔軟に対応してくれても…」というのが正直な気持ちでしょう。実際、不動産取引では、支払期日が1~2日ずれても、現場判断で対応して取引を進めるケースは多くあります。
ただし、契約書に違反している事実自体は否定できず、売主が「受領を拒否」すれば、買主側がいくら支払おうとしても決済を完了することができません。
訴訟を提起すれば、法的には「買主に重大な契約違反はない」と評価される可能性はありましたが、判決まで進めば少なくとも数ヶ月から1年以上はかかるでしょう。そのため、私たち弁護士の出番となりました。
民事調停の流れについてはこちらから。※裁判所のホームページに飛びます。
4.訴訟のリスクとコストを冷静に伝える
まずは、売主側が主張する「契約解除」の根拠と、法的にどこまで正当性があるのかを分析し、交渉戦略を立てました。裁判となれば、勝敗が確定するまでに時間も費用もかかり、何よりも感情的な対立が激化するおそれがあります。そこで、私は売主側にこう伝えました。
「このまま訴訟になれば、契約の有効性をめぐって法廷で争うことになります。結果は読めませんし、手付解約ではなく違約金支払いという結論になる可能性もゼロではありません。数日の遅延でここまで争うよりも、互いに一歩譲ってこの取引を前に進めた方が、将来的にも有益ではありませんか?」
一度に会長を説得するのは難しいと判断し、まずは現場担当者、次に実務を仕切る番頭さんへと順を追って説得し、最終的に会長にも納得いただけるよう粘り強く調整を続けました。
5.「譲歩」という選択が生んだ、穏便な解決
最終的には、以下の条件で再契約が成立しました。
・売買代金は当初の額通りに履行
・支払遅延分に対する若干の利息を上乗せ
・契約書の一部条項を再確認し、今後のトラブル予防策も協議
お互いの立場を尊重しつつ、柔軟に対応したことで、わずか数日で裁判リスクを回避できた形となりました。
れば、白黒つけるのに、お互いかなりの負担になると考えました。
6.トラブルから得た教訓:契約書と“人間関係”
この事例から学べるポイントは、大きく2つあります。
契約書は「紛争時のスタートライン」に過ぎない
契約書があるからといって、絶対にその通りに進むとは限りません。特に不動産取引のような高額な契約では、ちょっとした遅延や誤解が大きな争いに発展することがあります。
相手を「動かす」には、法だけでなく“信頼関係”がカギ
今回も、法的な正当性だけで相手を説得できたわけではありません。信頼関係の構築と、実務的な着地点を模索する姿勢があったからこそ、最終的に和解に至ったのです。
まとめ
「たった数日の遅れで契約解除?!」という場面でも、法律と交渉の力で解決は可能です。取引トラブルに直面したとき、感情的な対立に発展する前に、専門家のサポートを受けることで円満な解決が図れることがあります。
大切なのは、「契約書」と「対話力」、両方をバランスよく活かすことです。
【弁護士の一言】
こんなことで、弁護士にと思う方もいるかもしれませんが、どちらか一方が折れなければ、契約書に記載したことを実現するのには「訴訟」が必要になる可能性がある、という怖さを知っていただきたいと思った事案です。ルールを守る相手ばかりの世の中ではなく、「ちょっとしたボタンの掛け違い」で大きなトラブルになりかねないという教訓となる事案でした。
お問い合わせをご希望の方は下記のフォームよりお願い致します。