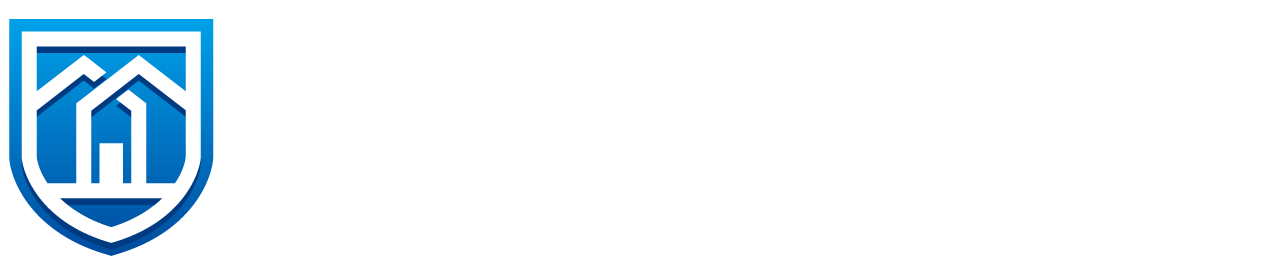中古物件購入後に「こんなはずじゃなかった…」と思ったら
中古不動産の購入後、「配管が繋がっていなかった」「水が流れない」「バルブが腐食して動かない」といった“見えないトラブル”が発覚することがあります。売主側の責任を問いたいと思っても、「これは老朽化の範囲?」「重要事項説明書に書いてあるから無理なのでは?」と迷うケースも多いでしょう。
本記事では、実際に神奈川県で発生した中古物件の瑕疵トラブルをもとに、売主に責任を問えるケース・問えないケースの境界線を弁護士がわかりやすく解説します。不動産仲介会社や買主にとって、トラブル回避に役立つ実践的な知識が得られる内容です。
宅地建物取引業法の解釈について(国土交通省のホームページへ飛びます)
1.【事例紹介】神奈川県の中古不動産で発覚した設備トラブル

買主側の仲介業者さまから、次のようなご相談を受けました。
- 散水栓が固まっており動かない。周辺の土が陥没している。
- バルブ類が腐食し、ハンドルが欠けている。いざというときに使えない状態。
- 雑排水の配管が接続されておらず、水路に水が溜まってしまう。
買主さまは「こうした瑕疵は知らなかったでは済まされない」と主張し、売主に修補を求めているとのことでした。
これに対し、重要事項説明書(重説)には「上下水道は老朽化しており、配管の取り換えや補修が必要になる可能性がある」と明記されていました。売主側は「老朽化の範囲であり、補修義務はない」として対応を渋っている状況でした。
2.【弁護士の見解】老朽化リスクは原則として買主負担

このようなケースでは、買主側の請求が法的に認められる可能性は低いと考えられます。理由は以下の通りです。
- 重要事項説明書にて老朽化のリスクが説明されている
- 中古不動産の売買では、経年劣化に関する設備不良は売買価格に反映されるのが原則
- 売主側に契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)を問うためには、明確な契約違反や隠蔽が必要
つまり、経年による腐食や未整備な部分があるからといって、必ずしも売主が補修費用を負担する義務はありません。
仲介業者が取るべき対応は?
仲介会社としては、以下のような対応が現実的です。
- 買主に対し、「法的には補修請求が通りにくい」旨を丁寧に説明する
- 信頼できる工務店等に相談し、修理費用の見積もりを安価に出せないか検討する
誠実な説明とサポートを心がけることで、買主との信頼関係を保ちつつ、トラブルを拡大させずに対応することができます。
3.【補足解説】老朽化以外の不備は責任追及できる?

下水配管が接続されていなかった箇所について、「老朽化とは関係ないのでは?」という追加相談もありました。これについては、唯一、交渉の余地があるポイントといえるかもしれません。ただし、以下のようなハードルがあります。
- 売主側が「老朽化が原因」と主張すれば、争いになる
- 水が溜まっている程度の不具合では、損害額を金銭換算するのが困難
- 裁判費用を考慮すると、訴訟での解決は現実的ではない
したがって、現実的な対応としては、売主側と穏便に話し合い、交渉で解決を図るのが望ましいといえます。
4.【弁護士の解説】中古不動産取引におけるリスクと価格の関係

中古物件では、「細かな瑕疵が後から見つかる」ことはよくあります。そのため、売買契約においては、契約不適合責任を免責する特約が付されていることが一般的です。つまり、買主は「安価に購入できる代わりに、ある程度の不具合は自己責任で対応する」前提で契約することになります。ただし、以下のようなケースでは、売主の責任を追及できる可能性もあります。
- 不具合の内容が建物の安全性を脅かす重大なものである
- 売主が瑕疵の存在を知りながら告げていなかった(悪意または重大な過失)
契約締結前には、重要事項説明書や契約条項の中身を丁寧にチェックし、不明点があれば遠慮なく質問・交渉を行うことが重要です。
まとめ:中古不動産購入には「リスクと価格」のバランス感覚が必要
中古物件では、引渡し後に細かな瑕疵が発覚することがあります。しかし、それらの多くは老朽化に伴うものであり、法律上の補修義務を売主に問うことは難しいのが実情です。今回のようなケースから得られる教訓は次のとおりです。
- 中古不動産の購入時には、一定の不具合リスクを想定すべき
- そのリスクは売買価格に織り込まれていることを理解する
- 契約前に免責条項や設備状況を十分に確認し、必要に応じて交渉する
不動産仲介会社にとっても、こうしたリスクを見越して説明責任を果たすことが、信頼獲得とトラブル回避のカギとなります。
【弁護士の一言】
トラブルにあっている買主側に冷たいように見えるかもしれませんが、「中古不動産」購入については、ある程度不具合があることを前提にした金額設定、という心構えをするのは非常に大切だと思います。これが新築や築浅であれば、契約不適合(瑕疵担保)で争う余地も比較的残されるのですが、築10~20年を経過した裁判例では、買主側敗訴の事例が非常に多いです。
決済後に起きると「法的トラブル」ですが、決済前ならば「金額交渉」で調整する余地もありますので、仲介・買主が連携して、不具合を見つけたら早期に調整・交渉していくのが大事だといえるでしょう。
お問い合わせは下記のフォームよりご連絡ください。