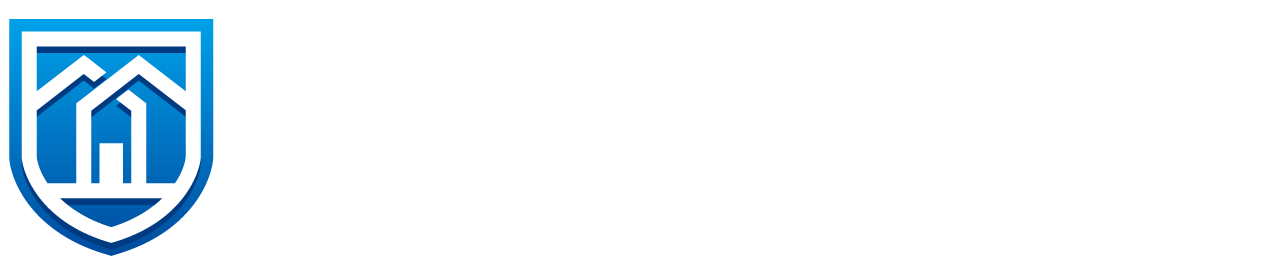2025年、ついに公証人法が大きく変わります。
令和5年6月に公布された「公証人法等の一部を改正する法律」により、公正証書の電子化やオンライン手続き、リモート本人確認など、公証制度がデジタル社会に対応した形へと進化します。
これにより、弁護士・司法書士・税理士などの士業はもちろん、不動産・相続・契約実務に携わるすべての関係者にとって、業務運用の見直しが不可避となります。
本記事では、改正公証人法の背景とポイントをわかりやすく解説し、士業・事業者として押さえておくべき実務対応と注意点を整理します。今後の制度施行に備え、正確な理解と準備を進めましょう。
1. 公正証書の電子化とリモート対応――手続はどう変わるのか?
今回の公証人法改正により、公正証書作成手続が大きく変わります。従来は、公証役場に出向き、紙の原本をもとに面前で手続を行うのが原則でしたが、改正後はオンラインによる申請・面談・交付が可能となり、手続全体の利便性が格段に向上します。
まず、公正証書の原本は電子データで作成・保存され、依頼者からの嘱託(申請)もインターネット経由で電子署名を付して行えるようになります。また、謄本や正本などの証明書も電子データとしての交付が選択可能になり、郵送や来訪の手間を省くことが可能です。
さらに注目すべきは、Web会議システムを活用したリモート手続の導入です。公証人が相当と認めた場合には、依頼者が公証役場に出向かずに、自宅や事務所から画面越しに面談や意思確認を行うことができます。対面・オンラインの選択制により、依頼者のニーズに応じた柔軟な対応が実現される点は、業務効率化の観点からも大きな意義があります。
※詳しい手続きはこちらの日本公証人連合会のホームページもご参照ください。
もっとも、一部の手続(例:保証意思宣明公正証書)についてはリモート対応が除外されており、制度全体の運用には慎重な判断が求められます。今後の政省令の整備や公証実務の動向を注視し、士業として的確に対応していくことが求められます。
2. 本人確認や証人の取り扱いはどう変わる?現場での実務影響
改正公証人法では、公正証書作成時の「本人確認手続」も大きく様変わりします。従来は実印と印鑑証明書による確認が基本でしたが、改正後はマイナンバーカードや運転免許証などの公的本人確認資料を提示し、電子署名をもって本人性を確認する方法が主流となります。
特にリモートでの公証手続においては、対面のような直接確認が難しいため、公証人が画面越しに提示された身分証と申請者の容貌を照合し、電子署名との整合性を確保することが求められます。これに伴い、公証人側の本人確認に対する慎重な判断力が一層重要になります。
また、公正証書作成において証人が必要なケースでは、その立会い方法も見直しが進んでいます。対面での同席に加えて、ウェブ会議システムによるリモート同席が認められる可能性があり、証人が遠隔地にいる場合でも柔軟な対応ができるようになります。ただし、証人の画面越しの存在が「立会い」と言えるのかという点や、録音・録画の記録保存の要否など、細かな運用ルールは今後の省令等で明確化される予定です(2025年現在)。
実務上は、これまで以上に依頼者や証人への事前案内が重要となり、士業としては説明責任やトラブル防止の観点から運用フローの見直しが不可欠となるでしょう。
※遺言書作成を基本から振り返りたい方はこちらの記事もおススメです。
3. 手数料の見直しと依頼者への説明――業務フローはこう変わる
今回の公証人法改正に伴い、公証人手数料令も見直される予定です。これは単なる制度変更ではなく、士業の業務フローや依頼者への説明に直結する重要な改定です。
まず、電子公正証書やリモート手続の導入により、新たな手続や機能に応じた手数料区分が設けられます。たとえば、電子データによる内容証明付きの正本・謄本交付など、デジタル対応に特有の費用が明文化される見込みです。
さらに、手数料の金額自体にも大幅な調整が加えられます。具体的には、200万円を超える高額な契約や複雑な法律行為に対しては手数料が引き上げられる一方、養育費や死後事務委任契約など、社会的配慮が求められる類型に関しては負担軽減が図られる方向で検討されています。
このような変化に対応するため、士業には「事前に手数料の概算を提示し、納得のうえで依頼を受ける」ことがより重要になります。特に、リモート対応や電子化による利便性の裏側で、「想定外の費用がかかった」といったトラブルを未然に防ぐには、説明の透明性と書面での確認が欠かせません。
まとめ
令和5年改正の公証人法は、公正証書手続の電子化・リモート対応を実現する大きな制度転換です。本人確認方法や手数料体系も見直され、士業には実務対応のアップデートが求められます。2025年中の施行を見据え、依頼者対応・業務フロー・説明体制の見直しを早めに進めることが、今後の信頼獲得とトラブル防止につながるでしょう。
【弁護士の一言】
今回の改正は、公正証書作成のデジタル化が進み、身体の御不自由な高齢者の方でも、比較的遺言書等の作成が容易になる側面もあり、時代に即した改正だと捉えています。もっとも、遺言書作成時には「意思能力」の判断において、かなりセンシティブな局面を迎える場合もあり、このような際に、電子による手続で、意思能力の確認が上手くできるのか、やや実務家としては懸念点もあるように感じました。
いずれにせよ、電子契約はじめ、法務も電子化の流れですので、「何となく難しそう」ではなく、私自身新しい制度をしり込みせずに利用できるように勉強していきたいなと感じました。
ホームページからのお問い合わせは下記からお願い致します。