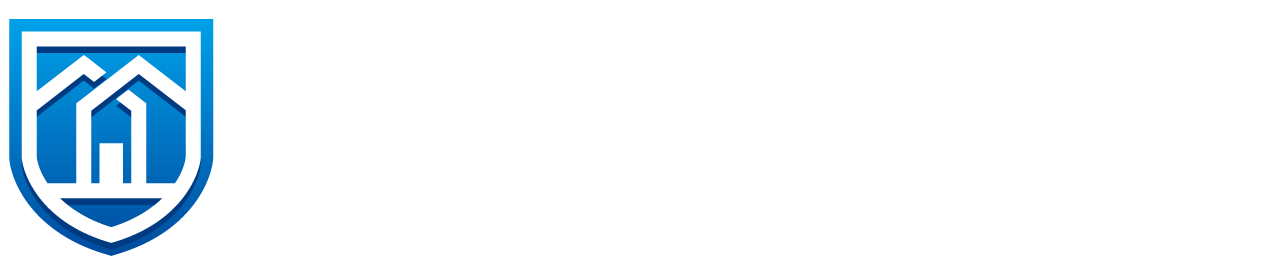1. 遺言書とは?
遺言書とは、被相続人(亡くなる方)が自身の財産の分配方法を決め、法的に有効な形で残すための文書です。適切に作成された遺言書があると、相続時のトラブルを防ぎ、円滑に遺産分割を進めることができます。
遺言書がない場合、遺産は法定相続分に基づいて分配されます。しかし、相続人同士で意見が食い違うことも多く、遺産分割協議が長引くケースも少なくありません。そのため、事前に遺言書を準備することが重要です。
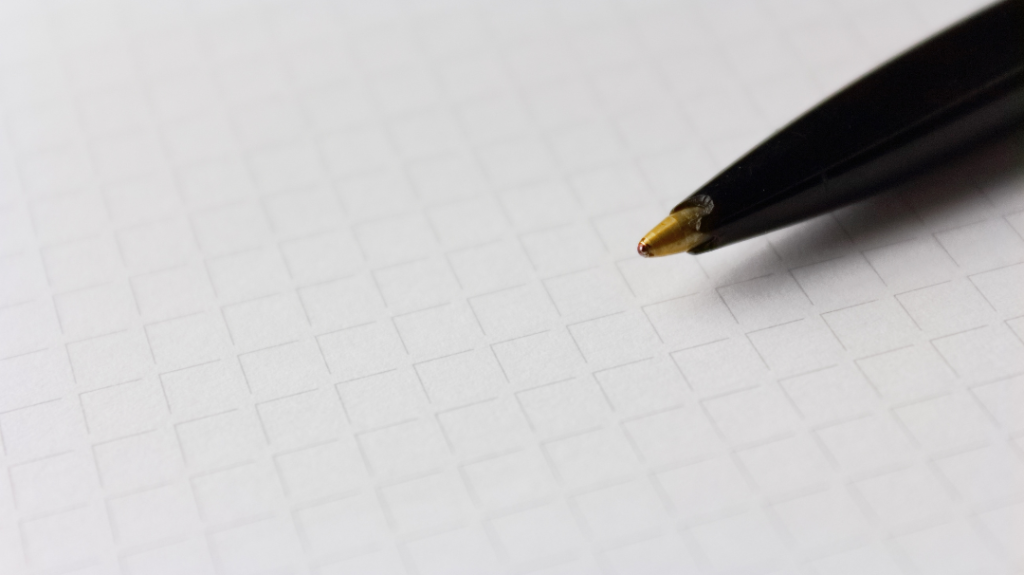
2. 遺言書の種類
日本の法律(民法)に基づき、遺言書には主に以下の3種類があります。
① 自筆証書遺言
【特徴】
本人が全文、日付、署名を自筆で記入し、押印することで作成します。
【メリット】
• 手軽に作成できる
• 費用がかからない
【デメリット】
• 形式不備があると無効になる可能性がある
• 紛失や改ざんのリスクがある
補足:2020年の法改正により、財産目録はパソコンで作成し、署名押印をすることで有効になりました。また、法務局の保管制度を利用すれば、安全性が高まります。
自筆証書遺言書保管制度について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
② 公正証書遺言
【特徴】
公証人が遺言者の意思を確認し、公正証書として作成します。
【メリット】
• 法的に確実で無効になるリスクが低い
• 紛失や改ざんの心配がない
【デメリット】
• 公証役場に出向く必要がある
• 費用がかかる(数万円~)
③ 秘密証書遺言
【特徴】
遺言書の内容を秘密にしつつ、公証人と証人2人の前で封印して作成します。
【メリット】
• 内容を誰にも知られずに作成できる
【デメリット】
• 方式の不備があると無効になる可能性がある
• 遺言書の存在が認識されないリスクがある
3. 遺言書の書き方
自筆証書遺言を作成する際のポイント
1. タイトルを明確にする(例:「遺言書」)
2. 遺言者の氏名を記載する
3. 財産の分配方法を明記する(誰に何を相続させるのか具体的に記載)
4. 日付を明記する(例:2025年3月14日)
5. 署名と押印をする
6. 訂正する場合は適切な修正方法を守る(訂正箇所に押印し、訂正したことを明記)
特に「誰に、何を、どのように相続させるか」を明確に記載し、相続人が迷わないようにすることが重要です。
4. 遺言書作成時の5つの注意点
- 形式不備に注意する
遺言書は法律で定められた形式を守らないと無効になります。特に日付や署名、押印の漏れに注意しましょう。
2. 遺留分を考慮する
相続人には最低限の遺産を受け取る権利(遺留分)があります。遺言で全財産を特定の人に渡すと、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
3. 保管場所を明確にする
自筆証書遺言は紛失や改ざんのリスクがあるため、安全な場所に保管し、家族や信頼できる人に存在を伝えましょう。
4. 証人の要件を満たす
公正証書遺言では2人以上の証人が必要です。未成年者や利害関係者は証人になれないため、適切な人を選びましょう。
5. 定期的に見直す
財産状況や家族関係の変化に応じて、遺言書を適宜更新しましょう。
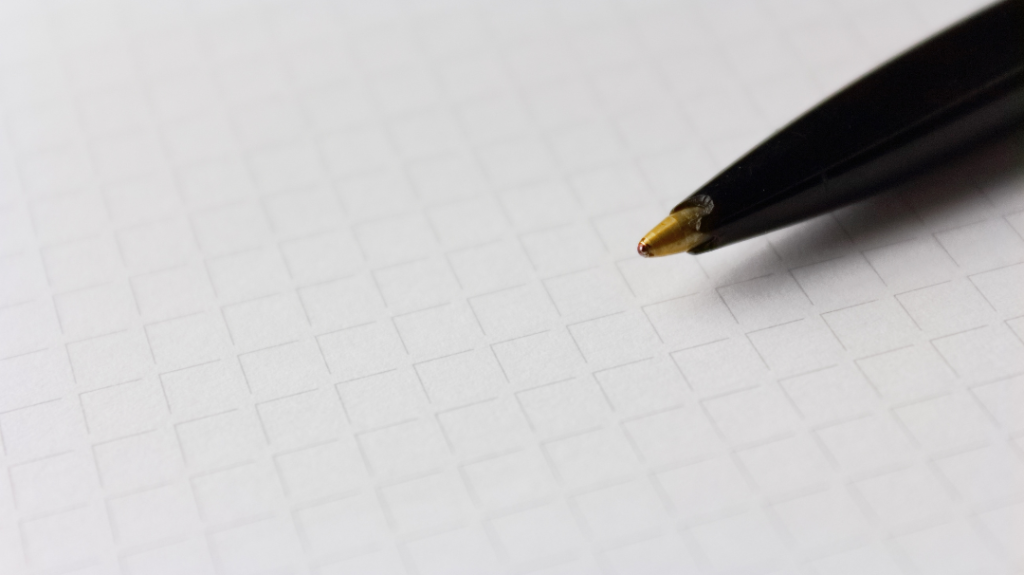
5. 相続手続きの流れ
- 死亡届の提出(7日以内)
- 遺言書の確認(家庭裁判所での検認が必要な場合あり)
- 相続人の確定と財産調査
- 遺産分割協議(必要に応じて)
- 相続税の申告・納付(相続開始から10ヶ月以内)
- 名義変更手続き(不動産・金融資産等)
相続税の申告・納付期限が10ヶ月以内である点は特に注意が必要です。申告が遅れると延滞税が発生するため、早めの手続きを心がけましょう。
6. まとめ
遺言書を適切に作成することで、相続人間のトラブルを防ぎ、スムーズな財産承継が可能になります。特に公正証書遺言を活用すると、法的に確実性が高まり、安心して相続対策を進められます。
また、相続には法律や税務の知識が必要となるため、遺言書作成や相続手続きに不安がある場合は、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
適切な遺言書を準備し、安心して未来に備えましょう。
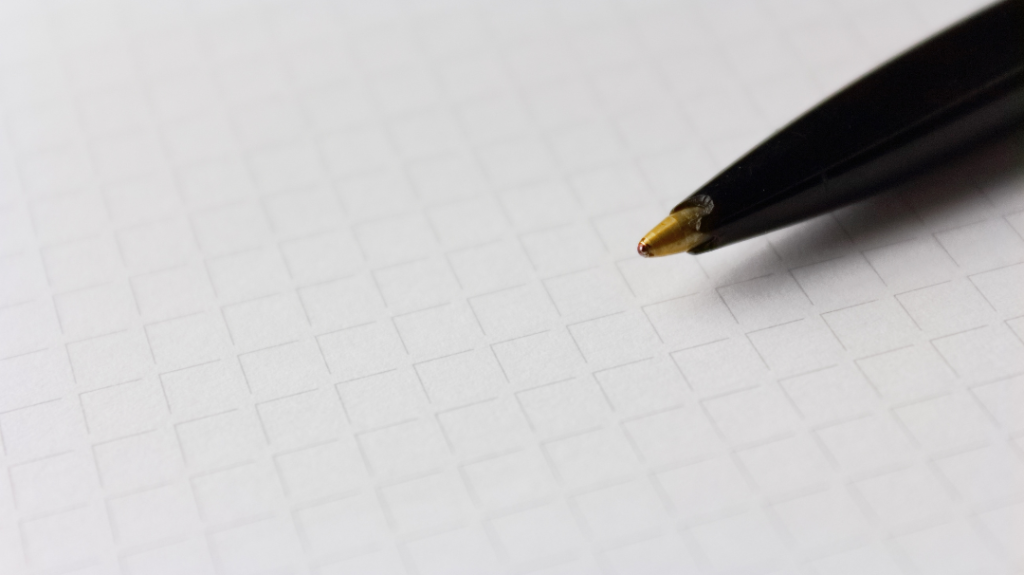
【弁護士の一言】
遺言書を作成しておかないと、法律は「法定相続分」という相続の割合しか決めておらず、具体的な財産の分け方は全く決まっていないことになります。そのため、遺産分割時には度々揉め事が生じてしまう原因になっています。また、遺言書に関しては、法律通り3つ紹介しましたが、秘密証書遺言は、ほとんど見たことはありません。手軽かつスピーディーに作成できる自筆証書遺言か、コストと時間がかかりますが、効果が安定する公正証書遺言かの2択だと思います。
記事としてはベーシックに遺留分に配慮するようにとしましたが、確実に揉めるような案件では、遺留分をあえて無視したような遺言書を作成するようなケースも多いです。
揉めそうな相続対策は、弁護士による遺言書対策が一番効果的だと思います。
【監修:弁護士 山村 暢彦】