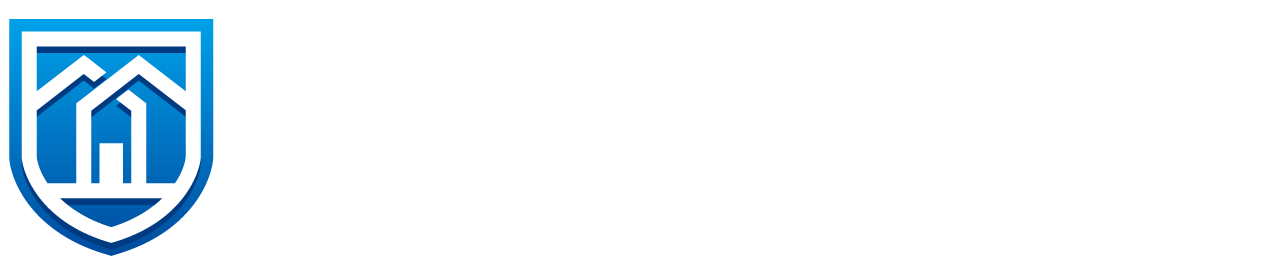「30年一括借り上げで家賃保証します」――。そんな甘い言葉に惹かれて始めたサブリース契約。しかし、いざ蓋を開けてみると、家賃の大幅減額や契約解除トラブルに直面するケースが全国で多発しています。
サブリース会社がオーナーに無断で賃料を引き下げた、不払いになったなどで訴訟に発展したなど、悪いニュースが尽きません。少子高齢化による空室増加、賃料下落圧力が強まる中で、「想定より儲からない」、「話が違う」といった声も増えています。
この記事では、不動産オーナーや投資家の皆さまに向けて、サブリース契約の仕組みとリスク、そして最新の法規制をわかりやすく解説します。
サブリースとは?その仕組みと特徴
サブリースとは、不動産オーナーが物件を「サブリース会社(管理会社)」に一括で貸し出し、その会社がさらに第三者(入居者)に「転貸(また貸し)」する契約形態です。
オーナー ▷ サブリース会社(マスターリース契約)
サブリース会社 ▷ 入居者(通常の賃貸借契約)
この構造によって、オーナーは入居者の有無に関係なく、毎月決まった「固定賃料」を受け取れることが魅力とされています。

メリットだけじゃない…。実際に起こっているトラブルとは
一見メリットが多く見えるサブリースですが、以下のようなトラブルが頻発しています。
賃料の一方的な減額
契約当初に「10万円の家賃保証」と言われていても、数年後に「家賃相場が下がったから7万円にします」と通告される例が後を絶ちません。契約書に「家賃見直し条項」が入っていれば、法的に有効とされる場合もあります。
契約解除の困難さ
オーナー側から一方的にサブリース契約を解除することは基本的にできません。解除には事前の通知や正当事由が求められ、違約金を請求されるケースもあります。
原状回復費用の負担
「管理は任せてください」と言われたのに、実際には退去後の修繕費やトラブル対応がオーナー負担だったというケースも。契約内容次第では、負担の大半をオーナーが背負うことになります。
法律による規制強化:2020年施行の「サブリース新法」
このようなトラブルの増加を受け、2020年12月15日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」を施行しました。いわゆるサブリース新法です。この中でサブリース契約についても以下のような規制が導入されました。
- 重要事項説明の義務化
▷ サブリース契約のリスクを契約前に説明することが義務化。 - 不当勧誘の禁止
▷「30年保証」など、実態と異なる誤認を招く勧誘が違法に。 - 契約の適正化指針
▷ 賃料減額や解除条件について、透明性のあるルール設定が求められる。
こうした法改正により、表向きにはサブリース契約が「クリーン」になったように見えますが、実務上のトラブルは今も多く、契約内容の細部まで精査する必要があります。
弁護士が教えるチェックポイント
サブリース契約を結ぶ前に、以下の点を必ず確認しましょう:
✅ 家賃減額の「見直し条項」があるか
✅ 契約期間と「中途解約」の条件
✅ 修繕・原状回復の費用負担は誰か
✅ 管理内容と報告義務の範囲
契約内容によっては、サブリース会社の対応が不誠実でも、法的には正当化されることがあります。署名前に、専門家によるリーガルチェックを受けることを強くおすすめします。
まとめ:安心のために“甘い言葉”に要注意!
サブリース契約は、確かに「空室リスクを軽減し、安定収入を確保する手段」として有効な一面があります。しかし、その裏には「一方的な減額」「解約トラブル」「原状回復負担」など、多くのリスクが潜んでいます。
契約書の一言一句が、将来的な収支やトラブル対応に大きく影響するため、サブリースを検討されている方は、必ず弁護士や専門家と相談しながら慎重に進めてください。
お気軽にご相談ください
「今の契約内容が不安」、「契約解除できるのか知りたい」など、サブリースに関するご相談は当事務所まで。まずはお気軽にご連絡ください。

【弁護士の一言】
サブリースというスキーム自体が悪いわけではないのですが、かぼちゃの馬車事件など、悪いニュースが続く印象です。サブリース自体では、業者側にあまり利益が残らないので、そのため、数年経過すれば、当初と違う賃料の減額や、業者が困窮して不払いになってしまう、ついには破産してしまう、という事件が起きました。
このサブリース新法も規制の一助にはなっていると思うのですが、あまり強硬的な法律とまでは言えません。そのため、あくまで注意喚起的なものです。「空室リスク」に怯える新米オーナーに対して、甘い言葉で不利益な契約を結んでくるような業者には要注意です。サブリース契約を締結した後は、あくまで「賃借人」の立場になるため、解除も難しいです。
このようなサブリース契約を締結する前に不安な方は専門家に相談しておくとよいでしょう。
【監修:弁護士 山村 暢彦】