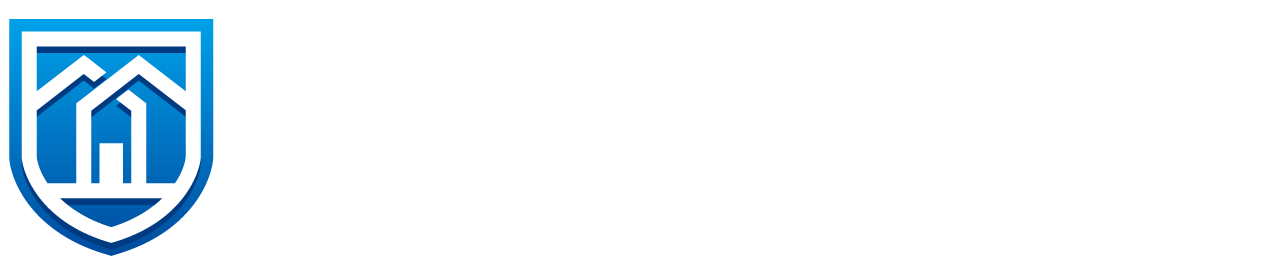不動産投資を成功させるには、相続・管理の視点も必要
不動産投資は長期的に安定した収益を得られる魅力的な資産運用方法ですが、投資家自身が突然亡くなってしまうと、遺族が予期せぬトラブルに直面することがあります。特に、複雑な投資スキームを組んでいる場合、相続人がその内容を理解できず、資産の適切な引き継ぎができなくなるケースが多発しています。
今回は、不動産投資家が突然亡くなった際に起こりうる問題と、それを未然に防ぐための対策を解説します。
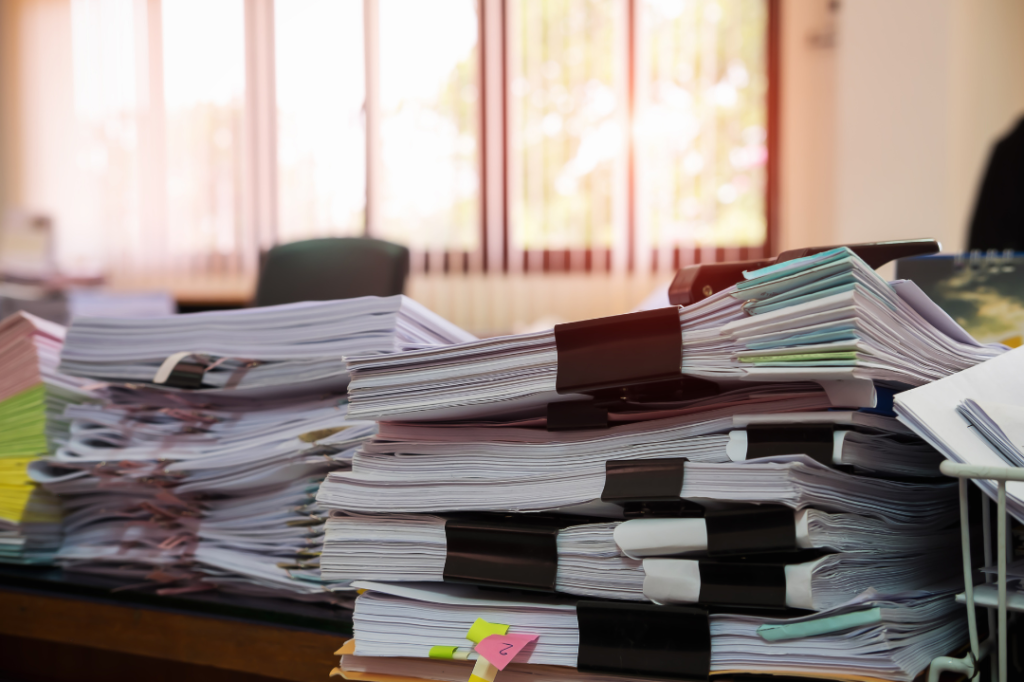
投資家の突然死がもたらす不動産トラブルの実例
ケース1|太陽光発電投資の契約が不明確
ある投資家は、地方の土地を購入し、太陽光発電設備を設置して収益を得ていました。しかし、生前に投資先の業者とトラブルがあったにも関わらず、契約内容を整理しないまま突然亡くなりました。
その結果、
• 親族が契約の詳細を把握できない
• 土地利用料や管理費の支払いの有無が不明
• 遺族が投資詐欺に巻き込まれる可能性がある
という問題が発生しました。
結果、相続人からすると、何が何やらわからないため、弁護士が介入して、契約関係の書類を開示請求しました。その上で、法的に何が要求できるのか、逆に何が要求できないのかを確認した上で、次の世代に負担にならないように、権利関係を整理する形で話を収めました。
ケース2|不動産管理の引き継ぎができずトラブルに発展
他にも、不動産賃貸業を営んでいた投資家が突然亡くなったケースでは、以下のような問題が発生しました。
• 収益物件の管理方法が不明確
• 入居者との契約状況が不明
• 共有名義の土地が処分できない
結果として、相続人は不動産を売却することができず、資産の凍結状態が続いてしまいました。
収益アパートを保有している状況で相続が発生すると、金融機関からの融資の返済や、管理会社から入退去の対処、賃料の支払い先の指定の問題などが生じます。管理会社としてはアパートの相続人が決っていないと賃料を支払うことができない、他方、金融機関は相続が発生しても月額の返済はちゃんとやってください、と板挟みになってしまうのです。
通常は、ある程度金融機関に返済をまってもらい、代表して賃料を受け取る方などを設定しますが、仲が悪い兄弟姉妹だとそれもできないようなケースもあります。その場合でも、代わりに弁護士が預かってくれるということなら了承が得られれば、この賃料の受け取りと返済を弁護士が代理して行うようなケースもあります。
意外と知られていないのですが、不動産投資家の急死はアパート経営に大きな支障をもたらすようなケースが多いのです。
不動産投資家が事前に行うべきリスク管理
不動産投資は単なる「資産形成」ではなく、「事業」であるという認識が必要です。そのため、事業の継続性を確保するためにも、以下の対策を講じることが重要です。
- 契約書・重要書類の整理
• 売買契約書、賃貸借契約書、管理契約書、ローン契約書などをファイリングし、相続人がすぐにアクセスできるようにしておく
• 投資スキームの内容や、毎年の収支をまとめた「資産管理ノート」を作成する - 法的対策の準備
• 遺言書の作成(特に、投資用不動産をどう分けるかを明確に)
• 家族信託の活用(相続発生後もスムーズに不動産を管理・運営できる)
• 相続税対策(相続発生時の税負担を抑える) - 共同名義の整理
• 共有名義の不動産がある場合は、事前に売却・分割・法人化などの対応を検討
• 家族会議を開き、資産の管理方針を共有 - 専門家への相談
• 弁護士・税理士・司法書士に定期的に相談
• 管理会社との契約を見直し、万が一に備える
• 事業承継計画を作成し、後継者を決める
まとめ|事前の対策が不動産投資の成功を決める
不動産投資は、適切なリスク管理を行わないと、資産を残すどころか、家族に多大な負担をかけてしまう可能性があります。
• 投資の仕組みを整理し、相続人が理解できる形にしておく
• 契約書や重要書類をファイリングし、すぐに確認できる状態にする
• 弁護士・税理士と連携し、相続トラブルを防ぐ
これらの準備を進めることで、不動産投資家自身だけでなく、その家族も安心して資産を受け継ぐことができます。
不動産投資に関する相続・資産管理のご相談は、専門の弁護士までお気軽にお問い合わせください。
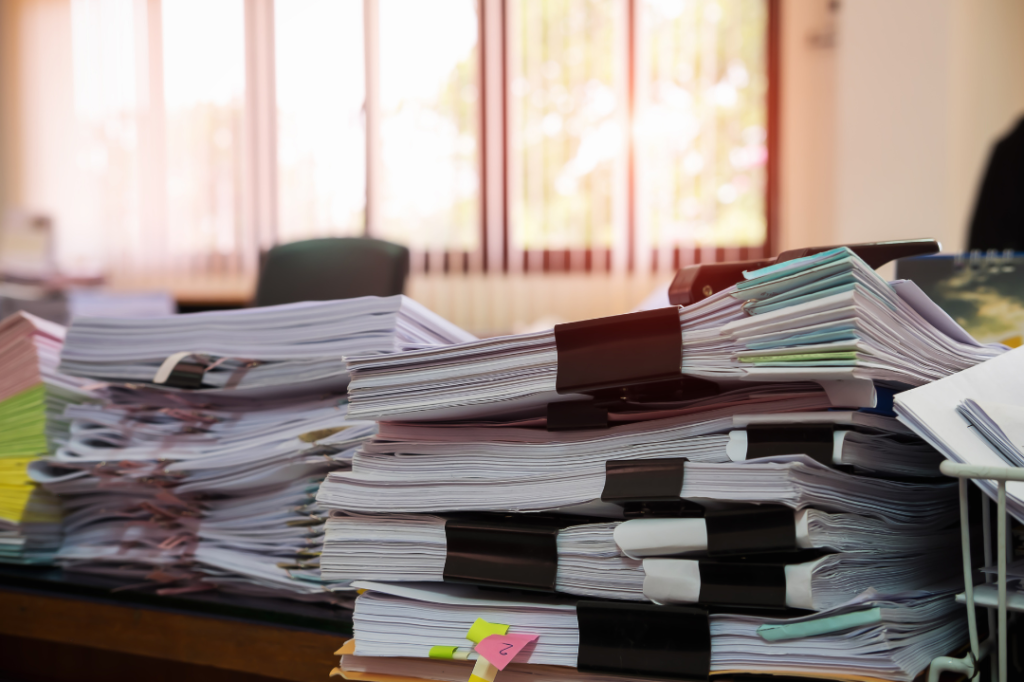
【弁護士の一言】
収益不動産を保有している方の急逝は、残された相続人の方が困ってしまうことが非常に多いです。賃料、原状回復、入退去などの大家業を止めないように配慮しながらも、遺産分割等の相続人間の話し合いを進めていく必要があります。
特に今回ご紹介したように、全く資料が残っておらずわけがわからない、という事案が多発しています。そのために、「不動産投資も事業だと考えて次世代に引き継ぐことが非常に重要」なのです。拙著第4章「相続:収益不動産の遺産承継の落とし穴」でも具体的な対策を述べていますので、ご参照いただけると幸いです。
【監修:弁護士 山村 暢彦】