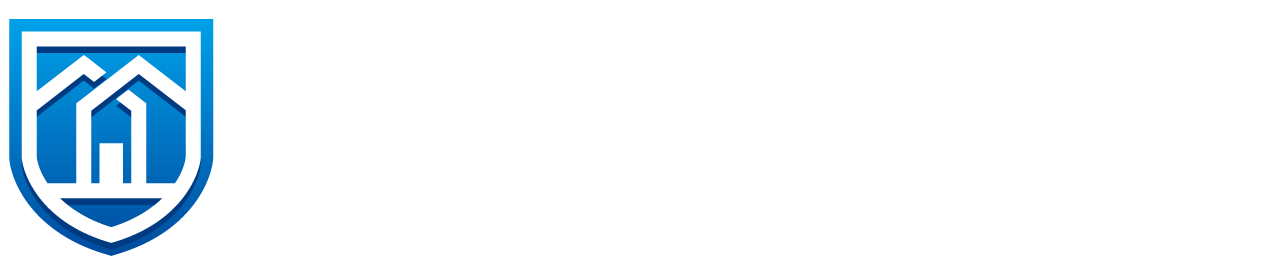都内近郊をはじめ、近年、土地を購入して新築の一棟アパートを建築するタイプの不動産投資が流行っていますが、一棟新築不動産投資を成功させるためには、建築工事契約の内容を十分に理解し、リスクを回避することが非常に重要です。特に、工務店や建設会社との契約書は、後々のトラブルを避けるために細部まで確認する必要があります。
建設請負契約は、国交省でもひな形が公開されています。だからこそ、ひな形を張り付けているだけの業者も多く、むしろリスクが多いので、ここにも注意が必要です。
【国土交通省HPより 建設工事標準請負契約約款について】
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000092.html
本記事では、建築工事契約の注意点について、具体的な条項の解説を交えながらご紹介します。
1.工務店側の責任範囲に注意|契約書の内容を理解する
建築工事契約書は、一般的に工務店や建設会社側の責任を限定する内容になっていることが多いです。これは、契約内容が一方的であることを意味するものではなく、むしろ、工務店がリスク管理をしっかり行っていることの証とも言えます。
例えば、《受注者の中止または解除権》は、業者が特定の条件下で工事を中止または契約を解除できる権利を定めた条項です。これは、工務店が不当に契約を終了させるためのものではなく、クレーム対応などのトラブルから自社を守るためのものであるケースが多いです。したがって、このような条項があるからといって悪徳業者とは限りません。むしろ、リスク管理のために必要な対応を行っている企業と見なすこともできます。
2.短期保証と工事後の対応|保証期間の内容に注目
建築工事契約には、「工事完了後の保証」に関する条項も含まれます。建物本体については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」によって、以下のように十年間業者側が責任を負いますので、契約段階で心配する事柄はそれほどありません。
(新築住宅の売主の瑕疵かし担保責任)
《e-Gov 法令検索》https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000081/
第九十五条
新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵かしについて、民法…に規定する担保の責任を負う。
2前項の規定に反する特約で買主に不利なものは、無効とする。
他方、建物の細かな設備については、設備のメーカーごとの短期保証(2年ないし3年程度の保証)の内容が定められているにとどまり、細かな不具合については保証対象外となることがあります。例えば、軽微な補修やメンテナンスについては、保証対象外とされることが多いです。
これにより、工務店が不具合を全て補修するわけではないことを理解しておく必要があります。
仮に契約書に、「ここまでの範囲しか軽微な修繕はしません。」と記載されている場合、「契約書に具体的な保証範囲が明記されていること」は、むしろそこまでは対応するという意味合いでもあるので、誠実な対応と捉えることもできるでしょう。このような契約書の内容をよく理解し、不具合発生時にどのような対応が求められるか、不動産投資家がどこまで費用負担してアフターフォローしなければならないかを確認しておくことが重要です。

3.工期に関するリスク|遅延損害金条項に注意
建築工事契約において、工期の遅延は大きなリスクの一つです。契約書の《遅延損害金》には、遅延が発生した場合のペナルティが記載されていることが多いです。ただ、現実的には、「遅延した理由が何か」、業者側の落ち度なのか、土地自体の問題、又は行政ないし近隣等の問題なのか等、遅延した理由が特定できないことも多いです。その場合、建設業者に工事遅延の責任を取らせることが難しく、工期が遅延した場合、施主側が不利な状況に立たされることが少なくありません。
遅延損害金が適用される条件や金額が明確でない場合、実質的に泣き寝入りせざるを得ないケースもあります。このような状況を避けるためには、契約書上の対処だけでは足りず、常に工事が進行中にも、「進捗状況を定期的に監督し、遅れが見られた場合は、迅速に督促を行う」ことが重要です。
4.工事代金と工期の変更に注意
また、請負工事契約では、工事の変更やそれに伴う工事代金の変更、工期の変更について定められていることが多いです。これらの条項は、一見すると特に問題ないように見えますが、実際には業者側に有利に働く場合もあるため、注意が必要です。
例えば、見積もりミスや工期の遅れを理由に工事代金や工期を変更する場合、施主側がその必要性を証明することは難しい場合が多いです。このような状況に対抗するためには、工事の進捗や見積もり内容を事前にしっかりと確認し、必要に応じて弁護士に相談することが有効です。
5.契約解除後のリスク
建築工事契約において、契約解除後の精算も重要なポイントです。契約を途中で解除して別の業者に引き継いでもらう場合、工事代金が大幅に増加することが多いです。このような状況になると、事実上「人質(ひとじち)」ならぬ「建物質(たてものじち)」をとられたような状態になり、施主が業者の要求に応じざるを得ないケースも多いです。
そもそも、解除せざるを得ないような関係性の建築会社が途中まで制作した建物を引き継いで工事してくれる業者を探すこと自体が、非常に難しいです。
契約解除を検討する際には、追加費用や精算条件について事前に確認しておくことが大切です。弁護士のサポートを受けながら、解除の判断を慎重に行うことが求められます。
まとめ|建築工事契約でトラブルを避けるために
新築建物の建築工事を伴う不動産投資を成功させるためには、建築工事契約の内容を理解し、リスクを回避することが不可欠です。契約書の内容を確認し、適切な対応を行うことで、トラブルを未然に防ぐことができます。特に「工期」や「工事代金」に関する条項は、事前に弁護士と確認しておくことが重要です。
また、見積もり金額が安すぎないか、もチェックポイントの一つです。過去には、破産事例も多く報告されているため、「安すぎる見積もりには注意」し、建設会社の信用情報(帝国データバンクなど)も確認することが推奨されます。
不動産投資家の皆様へ、建築工事契約でお困りの際は、ぜひ建築契約の専門弁護士にご相談ください。
【監修:弁護士法人山村法律事務所】